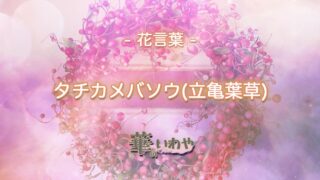 花言葉
花言葉 「タチカメバソウ(立亀葉草)」の花言葉とは?色や由来など花言葉を徹底解説
幅広の葉が可愛らしい「タチカメバソウ(立亀葉草)」は、ムラサキ科キュウリグサ属の多年草です。 日本の固有種で、北海道と本州に分布し、半日陰で水はけと風通しの良い、渓谷などに生育します。 花は白い花弁を5枚つけ、立った連なって咲きます。 花期...
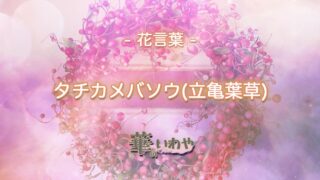 花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉 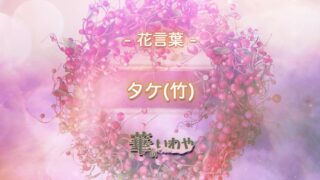 花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉  花言葉
花言葉